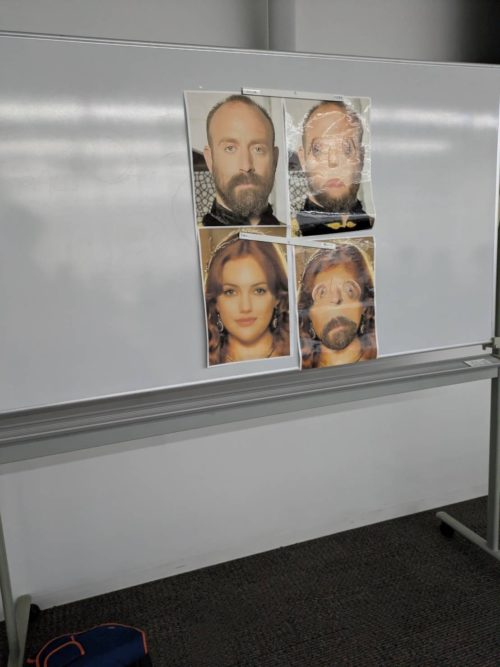脳が反応、聞いて慣れて自然習得~朝日新聞より東大教授・酒井先生の記事より~
2025年2月12日朝日新聞の記事に、ヒッポとMIT大と東大と共同研究していて、東大の酒井教授が書いたものが載っていたよ!とメンバーがシェアしてくれました。
ちょっと写真では、読みにくいと思うので、文字起こしすると…

言語習得と脳の働きを研究している酒井邦嘉教授によると、
脳科学において、人間の脳は、生まれながらに文の構造を把握できる「普遍文法」を持つという学説があります。これは、生まれた子どもが自然に言葉を覚える「自然習得」にもつながります。つまり、赤ちゃんと同じように多言語を自然に習得できる可能性が誰にでもあるのです。
私達の実験では、日本語を母語として第二言語として英語を習得している14~26歳の31人を対象に、文法を教えずに、なじみのないカザフ語の分を聞き続けてもらいました。その後、文法的な正誤を答えるテストを受けてもらいました。この時の脳を分析すると、テストの正答率が高い人は左のこめかみの奥、左脳の前頭葉の一部が活動していることがわかりました。
これはカザフ語を聞き続ける中で、文の構造を把握できるようになった人に見られた脳の反応でした。参加者は成人が大半だったことからも、大人になってからでもこうした自然習得ができることが示されました。
単語の暗記や文法の学習よりも、何度も発話を聞いて音に慣れていくことが大事だと思います。おすすめなのは、自分の好きな映画や歌で、繰り返し音を聞くことです。映画はどういう場面でどういう言葉を使うかがわかりやすいですし、歌は歌詞に感情がこもっています。長続きしやすく、一挙両得です。
単語や文法は、覚えることに頼るばかりの「勉強する」という考えでは、思ったほど身に付きません。自分の好きなことや、話さなければならないことから、少しずつ増やしていけば良いでしょう。
旅行が好きなら、観光で使う言葉だけでも構いません。100コの単語を無理に覚えようとして身に付かなくても、10個だけを完璧に使えれば、それを組み合わせて、いくらでも応用が利きます。
会話というのは相手がいて初めて成立するものです。相手を見て、自分のことばで伝えたいことを話そうとすれば、片言でも伝わるものです。(聞き手・市野塊)
酒井邦嘉先生 1964年生まれ。92年に東工大院理学系研究科博士課程修了。言語習得における脳の働きを研究しており、著書に「勉強しないで身に着く英語」などがある。
朝日新聞の外国語の扉という記事でした。
これを読んだメンバーからは、「酒井先生の記事、興味深いですね。人間は生まれながらに文の構造を把握できる。文の構造を習うより、自然習得で見つけだすのが話せる近道ですね!」と感想をくれました。